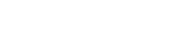叙述トリックといえば綾辻行人さんの「十角館の殺人」が有名ですが、同じく殊能将之さんの「ハサミ男」も代表作として挙げたい。
99年にメフィスト賞を受賞し、このミステリーがすごい!にもランクインされた作品で、個人的には十角館の殺人よりも好み。
視点や名前の絶妙トリックは、作者の罠にまんまとハマってしまう。しかも、もう一度読みたい気持ちが湧き上がってくるんですよね。

ここでは、ハサミ男のトリックをネタバレアリで考察します。なので「未読の方はご遠慮ください」と注意喚起しておきます。
ハサミ男のあらすじ
叙述トリック考察の前に、まずは簡単なあらすじのおさらいです。物語は、ハサミを使用した猟奇殺人犯・ハサミ男の「わたし」視点で進んでいく。
しかし、あるときハサミ男が次の標的にしようとしていた少女が、何者かにより同様の手口で殺されてしまう。
連続殺人犯であるはずのハサミ男が、「自分以外の犯人」を追いはじめていくという倒錯的な展開で進んでいきます。
叙述トリック
叙述(じょじゅつ)トリックとは、ミステリ好きな方には当たり前の概念かもしれませんが、一般には知らない方の方が多い(と思う)。

叙述トリックとは、文章や構成などを工夫して、読者にミスリードを誘うトリックの一つ。作者はさまざまな手法で読者を騙そうとします。

ハサミ男に使われていた叙述トリックは「人称トリック」になります。一人称の語り手をミスリードさせていました。
三つの視点
ハサミ男の叙述トリックを説明する上で、次の「三つの視点」に分けて考えていくと、分かりやすいと思います。
- わたし視点
- 警察視点
- マスコミ視点
構成配分は①と②がメインで、③のマスコミ視点は定食の漬物程度の存在感ですが、これがなかなかいい仕事をしているんです。
①語り手「わたし」視点
本作の最大のトリックは、語り手の「わたし」のミスリード。読者は終始、「わたし=男性の猟奇殺人犯」と思い込まされていた。
そのため、ハサミ男は日高光一だと錯覚します。しかし、実際のハサミ男は安永千夏(女性)であることが明かされます。
性別
まずは語り手「わたし」の人物像から。簡素でぶっきらぼう、まるで男のような話し方で読者をミスリードに誘います。
また、「わたし」の正体が男性ではなく女性だと判明する終盤では、女性が男性的性格においてフォローしています。
男みたいなしゃべり方をする女性は今どき珍しくもない。きっと性格も男性的なのだろう
出典:ハサミ男 殊能将之
ちなみに、犯人の男性的な話し方に違和感を覚えていた人物も登場していました。それが体育教師の岩佐でした。
「あんた、ひどく生意気な口のきき方をするな」
岩佐は私を睨みつけ、そんな捨て台詞を残すと、立ち去ろうとした。
出典:ハサミ男 殊能将之
犯人の男口調が、周囲に不快感を与える描写もありました。こうした違和感のある描写から叙述トリックを見抜いた読者は多そうです。
印象のズレ
一人称「わたし」視点において、他人の印象と自分の印象とのかい離(印象のズレ)がすごくうまく機能していたのが印象的でした。
犯人の安永は、自分が平均以上に美しいことに気付いておらず、また自分が太っていると過小評価する傾向がありました。
たとえば職場の上司佐々塚の接し方。
どうしてこの男はいつも相手の目を見てしゃべらないのだろうか
出典:ハサミ男 殊能将之
安永に好意があるため目をそらしてしまう。決してマイナスな印象ではないのだが、自己評価の低い安永は嫌われていると感じてしまう。
ほかにもこんなセリフがあります。
なぜ数学が得意なのに理科が苦手なのか。わたしのような頭の悪い人間にとっては、どちらも似たような教科にしか思えないのだが
出典:ハサミ男 殊能将之
頭の悪いと説明が入ることでマイナスに受け取りがちですが、数学と理科が似たような科目。つまり安永は「科目」の枠を超えて理解しています。

さらには、安永の自己評価の低さが、日高の人物像と合致していたことで、ハサミ男=日高とミスリードさせていました。
二重人格
ハサミ男を「二重人格」だと読者に思わせていたのもトリックの一つでした。堀之内のプロファイリングによってダメ押しされます。
これにより「わたし」の犯人探しは、「もう一人の別の人格のわたし」が犯行に及んでいたという可能性もちらつかせます。
殺害現場で拾ったライターに「K」とイニシャルが刻まれていたのも、日高光一を示唆するものであったといえます。

犯罪心理分析官、二重人格、幻聴、幻覚・・・心の病を連想させるワードが散りばめ、読者のミスリードを誘っていました。
②警察視点
序章では、一人称「わたし」視点からはじまりますが、第一章では三人称「警察」視点も織り交ぜながらストーリーは進んでいきます。
被疑者
警察がハサミ男の特定を誤認したことで(犯罪心理分析官の堀之内までもが誤認)、読者のミスリードをさらに加速させます。
警察は目撃者に疑いの目を向けますが、その対象は日高でした。警察視点で描く容疑者には、必ず日高光一が映っていた。
肥満を気にしていないのだろうか。いや違うと磯部は直感した。他人にまったく無関心なのだ。あの目はそういう目だ。櫛を入れた気配のない、ぼさぼさの薄くなりかけた髪もそのことを物語っていた。
出典:ハサミ男 殊能将之
このほかにも「希薄な印象」「白色のデブ」と警察の日高の人物分析と「わたし」との間における矛盾がないよう描きます。

警察の疑いの目=日高=「わたし」という関係式が出来上がると、なかなか叙述トリックを見破ることはできなくなってしまう。
磯部刑事
上井田刑事をはじめ目黒署刑事の面々らが今回の警察側の主要メンバーですが、その中でも磯部刑事が1つのカギになっていました。

捜査を進めるうえで鍵となる、きわめて重要な任務に赴いた、若手刑事の反応。それはどんな任務だろうか。たとえば容疑者の証言を聞くことがそうだ。
出典:ハサミ男 殊能将之
この場面は、若手刑事が安永(真犯人)に事件に関する証言を聞く場面。このときド緊張していたのが磯部刑事であった。
経験が浅いことから緊張していると思いきや、実は安永の美しさにソワソワしていただけだった。ここらへんの描写はユーモアがあって面白かった。
ちなみに、進藤刑事は安永を「ちょっと気味が悪かった」と鋭い分析をしていた。将来有望なのは磯部よりも進藤のようであるw
③マスコミ視点
もう一つはマスコミ視点。この作品では雑誌、テレビのメディアによる描写も描かれていて、こうした描写にもトリックが潜んでいた。
ハサミ男
もともと「ハサミ男」という通称を大々的に広めたのはマスコミです。堀之内も「ハサミ男」という名前を出して捜査をかく乱していきますが、
警察は
広域連続殺人犯エ十二号
と呼んでいました。
現場にハサミがあることから通称にハサミを付けるのは分かるが、なぜ「男」なのか、その明確な根拠は示されてないません。
容疑者に日高の名前は挙がっていたが、「男」と付けるにはいささか強引なのは明らかで、根拠が乏しいところ。

マスコミ先行にすることで、ハサミ「男」という装置を自然に潜り込ませています。さらに堀之内が通称として採用。
叙述トリックの定番中の定番である「性別」によるミスリードを、読者に連想されるリスクを限りなく低くしていました。
ちなみにタイトルの「ハサミ男」からして、読者をミスリードさせようとしています。
安永千夏の動機とラスト考察
ハサミ男のラストは次の通りである。
とても頭のよさそうな子だった。
「きみ、名前はなんていうの?」
と、わたしは訊ねた。
出典:ハサミ男 殊能将之
ハサミ男である安永が、次の獲物を見つけたところで終わることからも、彼女の殺人衝動は明らかに収まっていません。

結局彼女は興味の赴くままに殺人を犯していた。その興味の対象が「頭がいい」女の子。しかしその興味がなぜ犯行に繋がるのかは語られていません。
性癖か?心の問題か?それとも?ただ、ラストで安永の心の内が一瞬見える場面があります。
「いかん、ライオス王のお出ましだ。ぼくはあいつが苦手でね。このへんで失礼するよ」
医師は自分の部屋に返っていった。
すると、不思議なことに、看護婦に連れられて、病院の入口からふたたび医師がやってきた。いや、違う。医師にそっくりだが、医師とは別人だった。(中略)
知夏、あまり親に心配かけるものじゃない、と医師そっくりの男は言った。東京でひとりぐらしなんかつづけてるから、こんなことになるんだ。意地をを張らずに、そろそろ家に戻ったらどうだ。おまえが母さんのことで、まだこだわりを持っているなら...。
出典:ハサミ男 殊能将之
複雑な家庭環境を連想させます。
彼女に声をかけてきた医師は、父親を投影していました。また医師が父親を「ライオス王」と形容しています。
ライオス王はギリシャ神話に登場する人物で、わが子(オイデュプス)に殺されます。安永千夏の未来を暗示しているのか。
それともすでに・・・