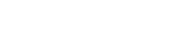慟哭(どうこく)は、作家・貫井徳郎さんが93年に発表したミステリ小説。第4回鮎川哲也賞の最終候補まで残るも受賞には至らず。
この作品をきっかけに作家デビューを果たし、それがバカ売れ、当時50万部を超える大ヒットになったんだとか。

とはいえ、本作を叙述トリックを使ったミステリ小説とは一概には言えない。それは主人公の境遇があまりの壮絶さと胸糞悪い読後感。
というわけで、ここでは慟哭のトリックや作者のメッセージなど、いろいろ考察していきます。ただしネタバレなのでそこは要注意。
叙述トリックを考える
彼の視点で描かれるストーリーと、佐伯の視点で描かれるストーリー、一見すると時系列は同じ平成三年とばかり思っていた。
実際は平成三年と平成四年と、一年の時系列にズレがあります。月日が(ほぼ)同じだったことで、同じ時間軸にいる「別人」と思い込んでいた。

トリックがバレバレという指摘
構成は数字により区切られ、「1、3、5...」と奇数章は「彼(=松本)」視点。「2、4、6...」と偶数章は「佐伯警視」視点で描かれます。
ただ、読んでみると、読者にトリックを隠している節がない。トリックのヒントがそこらじゅうに散りばめられているんですよね。
ミステリ愛好家、叙述ミステリ大好き読者には物足りない。あるいは、序盤でトリックを見破ってしまうことは、実際多かったように思う。
これについては改めて取り上げるとして、まずは作中に散りばめられていたトリックのヒントを集めていきます。
叙述トリックと作者の思惑
「いや、いまぼく横顔を見て気づいたんですけど、ぼく、どっかであなたとお会いしたことがありましたっけ?お顔に見覚えがあるんですが・・・」
出典:慟哭 貫井徳郎
私はこのとき頭は真っ白、犯人の「ハ」の字も思い浮かんでいませんでした。これだけなら、トリックを見破れなかったかもしれません。
ただ
「そういえば、私もどこかでお会いしませんでしたか」川上が口を挟んだ。
出典:慟哭 貫井徳郎
ともう一度同じセリフが。
えらい大胆だなと思ったわけです。こうも同じセリフがあれば、矛盾する点はあるものの、松本=佐伯とイコールで結ぶのは自然な流れ。
佐伯の家族、複雑な生い立ち、養子として佐伯の姓を名乗っているなど、中盤でほぼ一通り語り尽くしています。

養子ということは離婚すれば旧姓に戻る、現在捜査中の幼女連続殺人事件と関係していると考えていけば、それほど難しくないはず。
少なくとも、どんなトリックを使っているかはおいていて、松本=佐伯という繋がりは多くの読者が頭をかすめたはずです。
おそらく作者は、読者にトリックを隠すとか、犯人像を攪乱させるとかに、重きを置いていなかったのではなかろうか。
佐伯=松本の心の変化、新興宗教にハマり、娘を失った父親の痛々しい部分こそがメインであり、ミステリ作品なのかと?と思ったわけです。
タイトルから考える作者のメッセージ
ほかにも、純粋なミステリー作品とは言えない理由として、「慟哭」というタイトルからも考察できます。たとえば十角館の殺人。
叙述ミステリの傑作にして、クリスティの「そして誰もいなくなった」のオマージュ作品。十角館という孤島に佇む屋敷名がタイトル。
同じく、叙述ミステリとして有名なハサミ男。タイトルからすでにトリックが仕掛けられています。読者を騙す気マンマンなのが分かりますw

慟哭とは「声をあげて激しく嘆き泣くこと」、つまり誰かの感情を表しています。誰の感情かといれば主人公の叫びです。
耐えがたい虚無感、心にぽっかり穴が開いた心の状態。タイトルはその作品の顔ですが、本作はミステリ作品とは違うメッセージが汲みとれます。
社会派ミステリ作品
叙述トリックは、読者にとっては分かりやすい部類ですが、だから、この作品の構成が稚拙とは当然ながらイコールではありません。
構成が甘いのではなく(トリックは最高峰)、文章のところどころに分かりやすいフックがあらかじめ仕掛けられています。
タイトルの「慟哭」は松本の苦悩であり今作のテーマ。そのため、「叙述ミステリ」として読むと重すぎます。
ミステリ作品として本書を手に取ると、トリック以上に佐伯の心情が重くのしかかってきます。ルポやノンフィクといったリアルさすら感じます。

救われないラスト

「娘を―――恵理子を殺した班員は、判明したのでしょうか」
丘本は痛ましげに首を振った。
「いえ・・・・まだです」
出典:慟哭 貫井徳郎
やはり、私はトリックよりも松本の心境の変化に心を奪われる。松本は新興宗教を心の拠りどころにはしていない。
また宗教に救いなんて求めていない。松本が求めたのは自分の心を埋めてくれる存在。松本にとってそれが新興宗教だったってこと。
松本の新興宗教にハマっていった心境を一番よく現していたセリフがここ。個人的にはこのセリフがとてもゾワッとした。
「それは愚問ですよ、丘本さん。人は自分が信じたいことだけを信じるのです」
出典:慟哭 貫井徳郎
自分が納得したものは妄信的に信じてしまう。脳ミソなんてバグの多いヘッポコ器官、自分でさえ制御できないから困ってしまう。