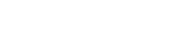ツイッターから個人情報がバレた話はよく聞くところです。以前に、写真から住所特定⇒自宅に押しかけてきたストーカーが話題なりました。
ストーカーさんからツイートから住所を特定するテクニック講座が送られてきた。皆様もお気をつけて。 pic.twitter.com/ZdiKtnKjdb
— zngo (@zngoron) 2016年2月20日
普通に笑えないガチ分析ですが、リツイートした人のコメントでそうだよなぁ~と思ったのが、

という指摘。
たった一枚の写真でさえこれですから、YouTubeならなおさら注意して、動画をアップしないとダメなのは言うまでもない。
[toc]
YouTubeで身バレするリスク

ヨウツベは、個人が発信する媒体の中でもトップクラスに、個人情報がバレる可能性が高いのは間違いないですね。
とくに広告収入で生計を立てている場合、ほぼ毎日投稿が必要になることもあり、個人情報が特定されやすいミスが起こりがちです。

自分では無意識でも、見る人からみれば、個人情報を特定するには十分なモノが映っているなんてことはよくあります。
動画から分かる主な特定分析
ここではあくまで「例」として上げますが、家バレだと時間がかかるものの、だいたいの地域くらいならすぐに特定可能です。
- 環境音
- しゃべり方
- 周辺環境を映す
- 制服・ジャージ
- 広告・食べ物・家具
- 部屋の間取り
環境音
環境音とは、動画に入ってしまう雑音のこと。たとえば救急車や電車、学校のチャイムなどがあり、ライブ時はとくに特定材料として有効です。
救急車のサイレンの頻度から、どのくらいの規模の都市に住んでいるのかの目安になったり、工事の音も使えます。
ある程度地域が絞りこめていたら、工事の音でさらに地域を絞り込めます。ほかにも参考になる環境音はありますが、このくらいにしておきます。

しゃべり方
配信者のしゃべり方は本人は無意識でしゃべっているので注意のしようがない。とくに方言ががある地域に住んでいる場合は特定しやすい。
最近だとVtuberの中の人特定ですかね。ニコ動からYoutubeに活動の場を変えてる方などは、バレやすいですね。

とくにこの界隈は、熱狂的なファンの方が多いと聞きますからね。詳しくは「Vtuber 元ニコ生主」で検索してみてください。
特定分析③周辺環境を映す
自宅の周辺環境を撮影するのは論外中の論外。怖いのは、子どもの成長記録をYouTubeにアップしている親御さんです。
地域のイベントや学校行事など、自身が住んでいる周辺を映した動画を、普通にアップしてるのをたまに見かけます。

しかも、こうした配信者の中には広告収入が目的ではなく、趣味や思い出を残す目的でアップしているから余計に怖い。
ネットリテラシーの高い若い世代
若い世代の動画配信者のほうがよほどしっかり自己防衛しています。ゲーム配信では、ゲーム画面のみを映し部屋は絶対に映さない。
部屋を晒すにしても、部屋の一室で固定カメラで撮影して、必ず壁を背にして撮影するなど、最小限の情報のみ公開していますよね。
特定分析④制服・ジャージ
制服は、地域ごと・学校ごとにデザインが異なっているので、通学している学校がカンタンに特定されてしまいます。
ほかにも、ジャージなどにある学校の校章からもでも特定が可能です。学校特定に関してはyoutubeよりもTikTokがカオス。

広告・食べ物・家具
日本テレビの「秘密のケンミンSHOW」を見ても分かるように、本人は当たり前でも、その地域独特の習慣があるものです。
たとえば、九州ではマルショクというスーパーが一般的ですが、関東圏にはまだ進出していないんですよね。
動画にこのスーパーの袋や広告、値札などから、配信者は九州に住んでいる(あるいは実家が九州にある)可能性が高い。
特定分析⑥部屋の間取り
地方では難しいんですが、都心に限っていえば、動画から間取を推測して特定することは比較的可能なようです。
引越しした数日後に、「住所をつきとめた」といった連絡が来たと報告するYoutuberは昔からよく聞くところ。
顔出しで身バレはほぼ回避不可
ちなみに、顔出しすることで身バレのリスクは格段に高まります。顔出しは人気者になるための要因になりえますがリスクも伴います。
いわば芸能人と同じです。住所特定はもちろんのこと、学歴、職歴の身バレリスクもグーンと上がってきます。

身バレ・住所特定回避方法

ここまでいろいろ書いてきたけど、身バレ回避は正直それほど難しくないです。ゲーム実況なら、ゲーム画面だけ映して声だけで配信する。
声配信したくないなら、ゆっくり実況みたいに音声合成ソフトを使うのもアリ。Vtuberになってもいいかも。
雑談配信であれば、カメラは固定で、必ず壁を背にして撮影する。テーブルなどの家具は反射しない素材のものを使用するなど。

顔出しするなら、身バレの覚悟は必要ですが、配信環境に気をつければ、住所特定まではそう簡単にはできませんので大丈夫。